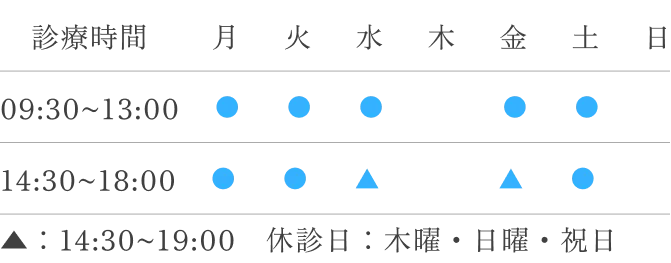受け口

「下の歯が上の歯より前に出ている」「前歯でうまく噛み切れない」といったお悩みをお持ちではありませんか?このような症状は「受け口」の特徴かもしれません。当院では、そうした受け口のお悩みに対して、適切な治療をご提供しています。
受け口とは

受け口とは、下顎(下あご)が上顎(上あご)よりも前方に位置している状態を指します。「反対咬合(はんたいこうごう)」あるいは「下顎前突(かがくぜんとつ)」と呼ばれる不正咬合の一種です。また日本人は欧米人と比較して骨格性の受け口が出現しやすい傾向があります。
受け口の特徴として以下のようなものがあります。
①下顎が上顎に対して前方位にある
②前歯部での食物の切断が困難
③特定の子音の発音が不明瞭になることがある
④側貌のバランスが損なわれる
⑤咬合時の違和感
上記のお悩みがある方はぜひ一度ご相談ください。
受け口の原因
受け口には複数の原因がございます。
遺伝によるもの
受け口には強い遺伝的傾向が認められます。ご家族に受け口の方がいる場合、遺伝的素因により同様の特徴が表れやすくなります。
乳歯から永久歯への生え変わりの問題
乳歯から永久歯への交換時期において、歯の生える順序や位置に異常があると、受け口の原因となり得ます。特に上顎前歯が舌側に生えたり、下顎前歯が唇側に生えたりすると、咬合関係のバランスが崩れ反対咬合を生じることがあります。
幼少期の癖
発育期における以下のような口腔習癖が受け口形成に影響を及ぼすことがあります。
①無意識に下顎を前方に突出させる習慣
②舌で下顎前歯を持続的に圧迫するような習慣
③猫背などの不良姿勢は二次的に咬合関係に影響することがあります
顎の成長バランスの乱れ
上顎と下顎の成長速度や最終的な大きさの不均衡により、受け口の傾向が顕著になることがあります。特に思春期・成長期においてしばしば観察されます。
外傷や疾患によるもの
顎顔面領域の外傷や関節疾患により顎位が変化し、二次的に受け口になることがあります。また稀ではありますが、内分泌疾患などの全身疾患が顎骨の成長に影響を及ぼし、骨格性反対咬合を引き起こす場合もあります。
受け口を治療しないとどうなる

受け口は審美的問題だけでなく、口腔機能にも様々な影響を及ぼします。適切な時期に治療介入しない場合、以下のような機能的・形態的問題が生じる可能性があります。
咀嚼機能の低下
反対咬合の状態では、前歯部での食物の切断効率が著しく低下します。これにより咀嚼の第一段階である切断が十分に行えず、食物の粉砕効率全体が低下することがあります。また臼歯部の咬合接触関係も不安定になりやすく、咀嚼効率の低下や消化器系への負担増加につながる可能性があります。
話し方や発音への影響
受け口では特にサ行、タ行などの発音が不明瞭になることがあります。特にお子さんの場合、発音の癖が定着してしまうと、歯並びが改善された後も発音の問題が残ることがあります。
あごの関節への負担
不正咬合は顎関節に負荷をかけます。その結果、顎関節症(顎関節内障)などの原因となる可能性があります。
歯や歯ぐきへの悪影響
受け口は特定の歯に過度に負荷をかける可能性があります。また、不正な歯列では適切な口腔衛生管理が困難になりやすく、虫歯や歯周疾患のリスク上昇にもつながります。
加齢に伴う症状の悪化
軽度から中等度の反対咬合であっても、年齢とともに症状が悪化する傾向があります。
当院で行う治療
当院ではまず詳細な診断資料を収集し、患者様の状態を多角的に評価します。その後、年齢、生活環境、希望する治療期間、経済的要因なども考慮し、最適な治療計画を立案します。
治療経過中も定期的な評価と必要に応じた計画の微調整を行います。
受け口 よくあるご質問

-
Q治療開始の最適な時期はいつですか?
- A受け口の治療開始時期は、症状の種類や重症度によって異なります。
一般的には、永久歯の萌出が始まる混合歯列期(6〜8歳頃)に初回評価を行うことをお勧めしています。特に骨格性の問題が疑われる場合、思春期成長期(女児7〜12歳、男児9〜14歳頃)の介入が効果的です。
一方で乳歯列でも反対咬合が発現したらすぐに治療開始することをおすすめします。
※早ければ5歳頃に治療が必要な場合もあります。
しかし、成人期であっても適切な治療により咬合と審美性の改善は可能です。
まずは専門医による適切な診断を受けることが重要です。
-
Q治療期間はどのくらいですか?
- A治療期間は、症状の複雑さ、年齢、選択する治療法によって個人差があります。
成長期の小児に対する初期治療では、通常1〜2年程度の積極的治療期間の後、経過観察期間が続くことがあります。
成人の矯正治療では一般的に2〜3年程度を要しますが、外科的矯正を併用する場合は術前矯正、手術、術後矯正と段階的に進めるため、全体として2〜3年以上かかることがあります。
初診時の診断で、個々の症例に応じた治療期間の見通しをご説明いたします。
-
Q保険は適用されますか?
- A受け口の治療は、症状の程度や治療法によって保険適用範囲が異なります。
特に「咬合異常」として厚生労働省の基準を満たす骨格的な問題が認められる場合、一部の治療に保険が適用されることがあります。ただし、審美的改善を主目的とする場合や、特定の矯正装置を選択する場合は自費診療となります。
初診時の診断後、適用可能な保険診療と自費診療の内容や費用について詳しくご説明いたします。
-
Q治療後のメンテナンスは必要ですか?
- Aはい、治療後の保定期間は治療結果の安定のために非常に重要です。一般的に保定装置(リテーナー)を指定された期間使用していただきます。
また、定期的な経過観察により、咬合関係の安定性を長期的に維持することができます。特に成長期の患者様では、残存する顎成長に伴う変化を評価するために、治療後も継続的な観察が推奨されます。
当院では、受け口でお悩みの方に対して、丁寧な診断とひとりひとりに合った治療計画をご提案しています。咀嚼・発音といった口腔機能の向上も含めた総合的なアプローチにより、患者様のQOL向上を目指します。受け口に関するご不安やご質問がございましたら、どうぞお気軽に当院までご相談ください。